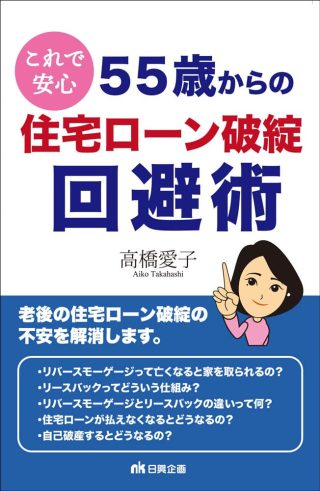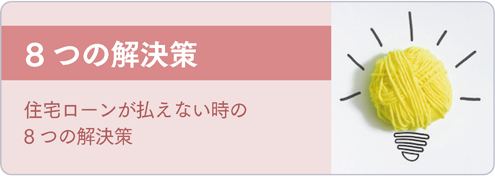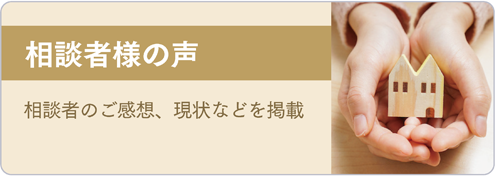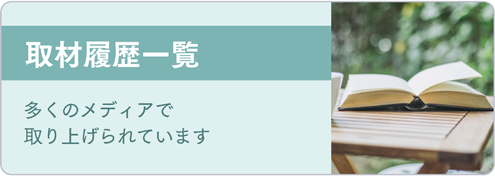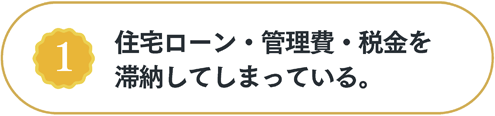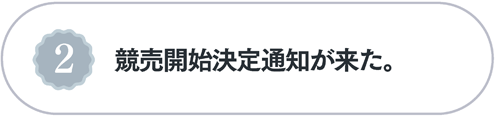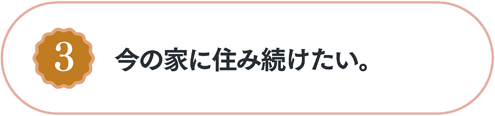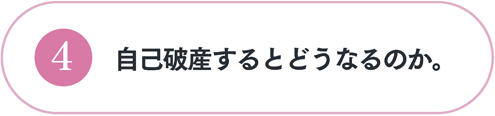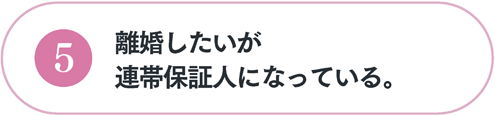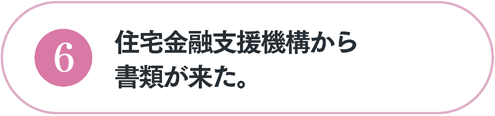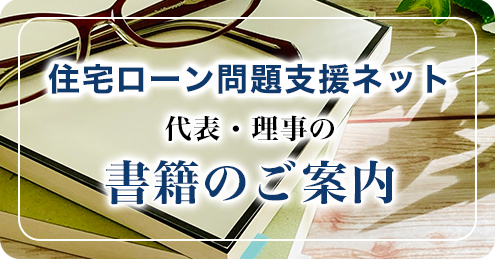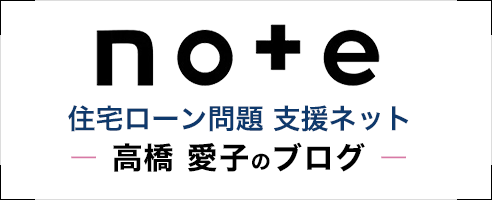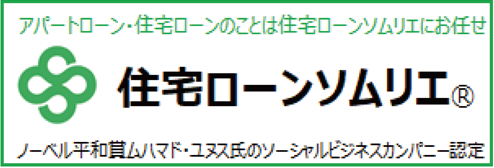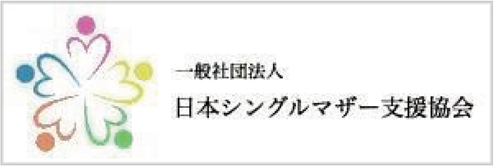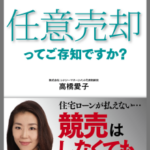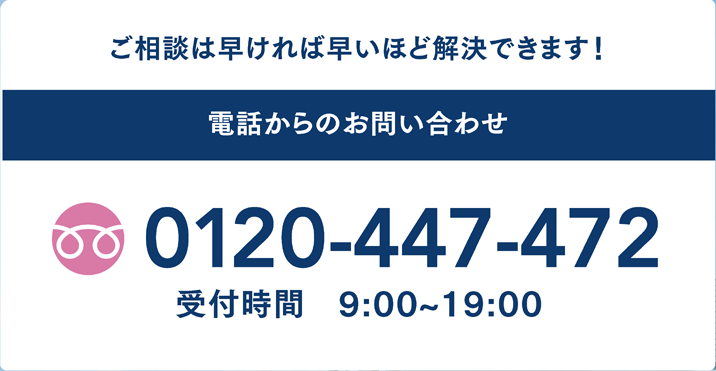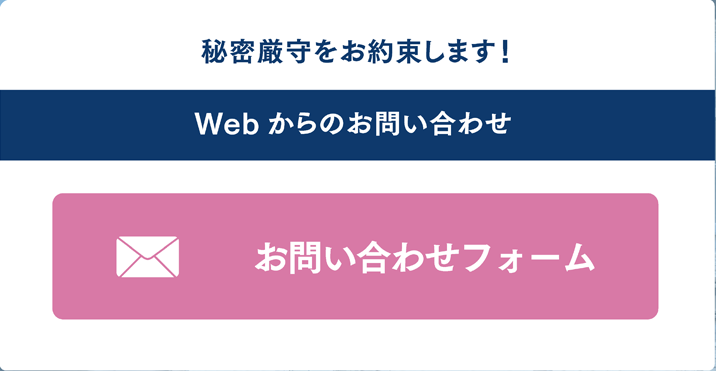住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
何度かこのブログでも書いていますが、近年、不動産のリースバックという手法はそんなに珍しいものではなくなってきました。これ自体は1960年代に始まったと言われますが、一般消費者向けのサービスとして認知されだしたのは、メディアでの広告が増えてきた2010年頃からのことです。
リースバックとは、自宅を売却してその代金を得ながら、売却後も買主と賃貸借契約を結ぶことで、そのまま自宅に住み続けられるという仕組みです。高齢化社会が進むなかで、住宅資産を活用した資金調達のニーズが高まっていることも、リースバックが広がった背景にあると考えられます。
人は、さまざまな事情を抱えているものです。問題を解決するためにリースバックを活用することに、もちろん私は、何の異論もありません。ただ、どんなに有効と思われる方法でもデメリットは必ずありますから、リースバックを実行に移す前に、メリットとデメリットについてはきちんと理解しておいていただきたいと思います。
5つのポイントを理解する
リースバック契約において気をつけるべきことには、大きく次の5つがあります。
①契約条件・賃貸借契約の確認
*賃料水準
:売却価格に比べて家賃が相場とかけ離れていないか。将来的に支払いを継続できるかを検討する。
*契約期間
:「普通賃貸借契約」か「定期賃貸借契約」かで、大きく異なる。「定期賃貸借契約」であれば、満期になった後、「再契約」できるかを必ず確認する。
*更新条件
:更新料や再契約の合意が必要かどうか。更新拒絶になる場合の要件(正当事由など)も整理しておく。
*敷金・保証金
:リースバック後の借主負担の修繕、退去時の原状回復義務の取扱いはどうなるのかを明確にしておく。
②売買契約上の留意点
*売却価格の妥当性
:売却価格は市場価格より低めに設定されるケースが多いため(概ね、市価の80~70%が目安)、査定根拠を確認する。明らかに安い場合は再検討のポイントになるが、高い場合では再売買時も価格が高くなるため注意が必要。
*買戻し特約(再売買予約)
:将来的に買い戻す予定がある場合、契約書に明記しておく。買戻しできる人は誰なのか、買戻しまでの期間等。
*引渡条件
:抵当権抹消、残債処理、引渡し時期の取り決めを明確にしておく。
③税務・会計面
*譲渡所得税
:通常の売却の場合と同様に課税される。特に短期譲渡の場合は税率が高くなる(ただし、自宅の場合は3000万円の特別控除が利用できる)。
*消費税
:建物部分に課税対象となるケースがある。按分方法に注意が必要。
*固定資産税
:引渡日を基準に日割り精算されることを確認しておく。
*贈与税
:明らかに安い取引の場合、「低廉譲渡」で贈与とみなされる可能性があるので要注意。
④法務リスク
*契約不適合責任の範囲
:これは、引き渡された物件が、種類、品質などに関して契約の内容に適合していない場合に売主が負う責任のこと。つまり契約書に書かれている内容と実際の物件が合っているかどうかが判断基準となる。リースバックでは免責にしておくのが一般的だが、調整が必要な部分。
*登記関係
:買戻特約や賃借権の登記をするかどうか検討。
*債権者対応
:債務超過の場合、住宅ローン債権者、抵当権者の合意を得る。後からリースバックが判明すると問題になるケースもある。
⑤買手の信頼性
*リースバック事業者の特性を検討する
:不動産業者、リース会社、不動産担保ローン金融機関、ファンド会社、不動産投資家(法人、個人)など、買手の種類は多岐にわたる。どの相手が自分の目的においてベストなのか慎重に検討する。
*リースバック事業者の目的を理解する
:定期賃貸借契約の場合は転売を目的としているケースもあるため、再契約ができるかの確認は必須。一方、短期のリースバックの場合は、転売目的かもしれないが売買価格は高い。長期設定の場合は転売よりも長期での賃料収入が目的で利回り重視となる。
*買主は借入をして購入するのか否か
:信用性の低い法人や個人の場合、最悪の場合は「抵当権の実行(競売)」で追い出される危険性もある。
最も大切なのは「自分はどうしたいのか」
リースバックは、「資金調達」と「住み続けたい」というニーズを共に叶えることができる優れた手法ですが、こうして見ていくと、メリットとデメリットが表裏になっていることもおわかりいただけると思います。当NPOでも、リースバックによるトラブルでのご相談は全体の上位を占めているのが実情です。
では、リースバックを選ぶ際に、最も気をつけておかねばならない、大切なことは何でしょうか。
私がこれまであらゆる相談者の方のお話をうかがってたどり着いたひとつの結論。それは、何のためにリースバックをするのか、その目的や希望を自分自身でしっかりと考え、理解し、納得しておくこと。これに尽きるということです。
目先なのか、終生なのか、買い戻すのか
目的が、たとえば「とにかく今、現金が必要で、あと1年だけここに住めればいい」であれば、定期借家契約で、なるべく高く売却できる買手を探すべきだと思います。しかし反対に、「この家を終の棲家として、終生住みたい」ということであれば、安定した普通賃貸借契約で、ずっと更新可能な契約形態でよいという相手に買ってもらう必要がある。また、リースバックをするけれど、将来的に親族に買い戻しをさせたい場合は再売買の条件も重視しなくてはなりません。
最近、事業再生の現場で割といらっしゃるのが、「いまは手元の資金が至急必要なので一旦リースバックで売るけれど、数年後には絶対に買い戻したい」と言う経営者の方です。買い戻しを現実的な目標、計画の一環として置いているため、このような場合は最初から買い戻し金額もイメージしておく必要があります。売却価格があまり高過ぎると買い戻し金額も高くなりますから、その見極めは重要です。
「買手の信頼性」は売主の将来にも影響大
今回挙げた5つのポイントのなかで、特に大事なのが5つ目の「買手の信頼性」です。
リースバックの事業者は、不動産業者、リース会社、不動産担保ローン会社、ファンド会社、不動産投資家などさまざまですが、いずれも事業者ですから、それぞれ目的があります。たとえば不動産業者の場合はマンションしか、あるいは戸建てしか買わないということもある。基本的にはリースバックで保有後に転売を目的にしているケースが多いので、普通賃貸借契約や、定期借家契約の内容はしっかりと確認する必要があります。
先ほども書いたように、短期設定でのリースバックは転売目的のことが多いですが、反面、売却金額は高くなることもありますから、売主の事情によって、一概にそれは勧められないとは言い切れません。一方で、長期設定の場合は利回り重視の投資家の場合が多く、転売はあまり考えていないことが多い。
また、いわゆる「信用性の低い」法人や個人投資家が借入れして物件を購入することもありますが、現金で買ってくれれば心配はないのですが、物件購入時に金融機関等から借り入れをして物件を担保に入れる場合は、後々、買主の財政状況が破綻し支払いが滞ると物件が競売になることがあり得ます。こうなると、売主がいくら「リースバック契約をしています」「買い戻し契約もあります」と主張しても契約書はすべて無効。競売落札者には対抗できないですから、家を追い出されることになってしまうのです(民法395条により明け渡しまでには6ヶ月間の猶予あり)。実際、当NPOへはこういった相談例もありました。
脅かすつもりはありませんが、リースバックはメリットもデメリットもある分、適正な買手を探すことが肝要にもなります。個人で見つけることはハードルも高いですから、少しでも不安に思うことがあれば、当NPOにご相談ください。中立的な立場で、リースバック事業者のご紹介や、アドバイスをさせていただくことも可能です。
「住宅ローンが払えない」というご相談をはじめ、離婚問題、相続問題、債務問題、不動産トラブル、投資物件トラブル等でもお困りのことがありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。ご相談内容に適したアドバイス、専門家の紹介も行っています。まずは何でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
メール、公式LINEでのご相談は24時間受付可能。関東・銀座相談所は、土・日・祝日の無料相談会を行っておりますので、対面や電話でのご相談予約も可能です。
相談所は、関西、中国・四国にもございます。ご相談の場合は各相談室にお問合せください。
【10月の土日祝日無料相談会】
10月12日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
10月19日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
10月25日(土)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
※面談時のマスク着用は、任意とさせていただきます。
電話、メール、オンライン相談(zoom)もご予約可能です。
【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:
https://www.shiennet.or.jp/database2/contact/