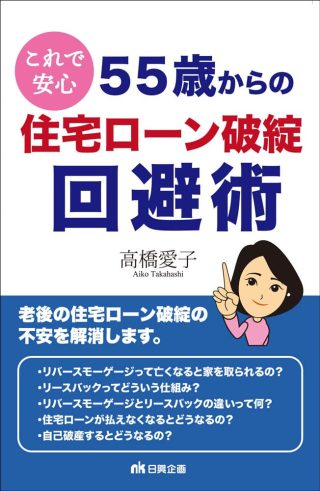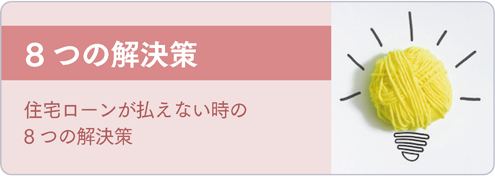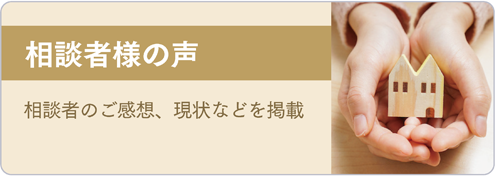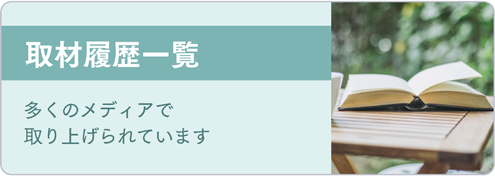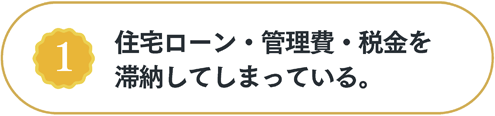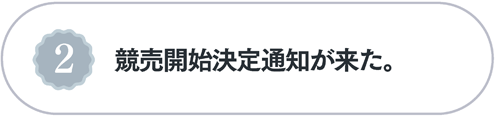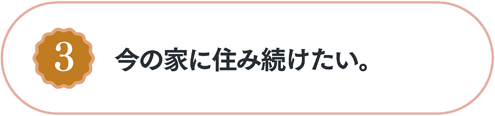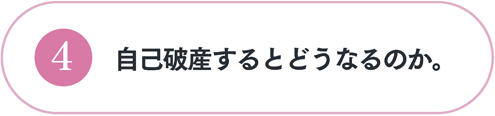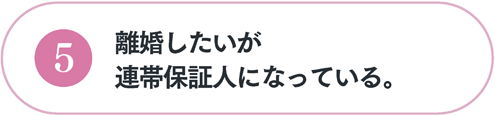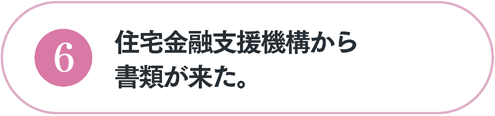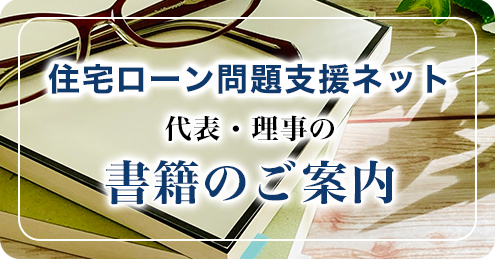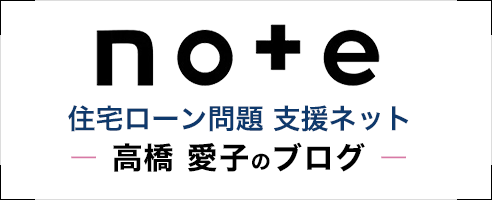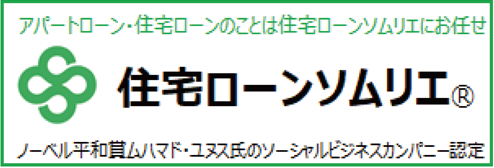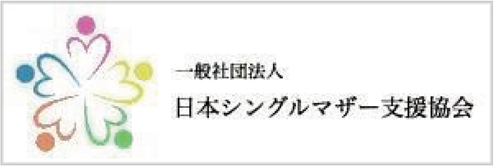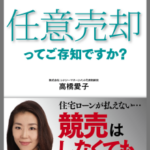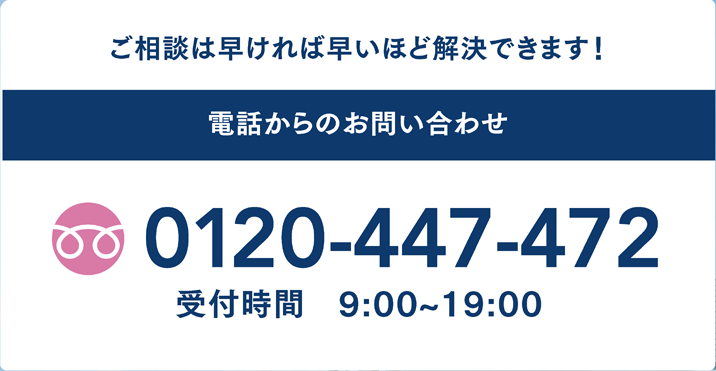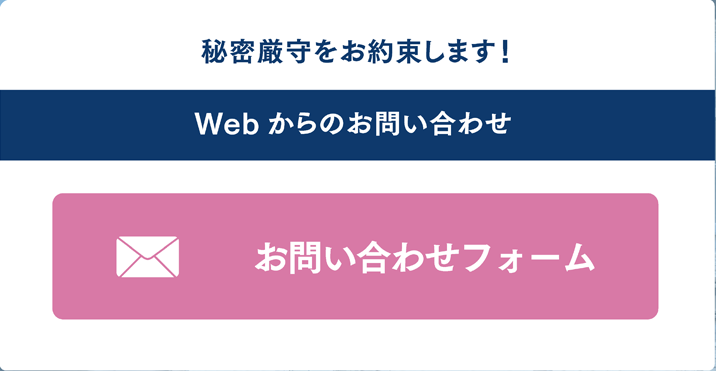住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
このブログでも何度か書いたことがある投資物件トラブルの話。中でも比較的多いのが、「住宅ローンを使って不動産投資物件を購入してしまった」という件です(ご参考までに過去のブログはこちらとこちらから)。
不動産投資のためのローンは、住宅ローンとは別物です。
住宅ローンは個人の居住目的での物件購入のためのものですが、不動産投資ローンは賃貸経営によって収益を得るための物件購入用に組まれるもの。両者は金融機関の審査も違いますし、借入れできる金額の上限、金利も異なります。住宅ローンを使って不動産投資物件を購入することは金融機関との契約上、「資金使途違反」と見なされ、一括返済を求められることもあります。
2ヶ月ほど前にも、「悪徳不動産業者に騙されて、住宅ローンで投資物件を買ってしまった」という20代の方と、その親御さんからのご相談がありました。その業者とは年明けからまったく連絡が取れなくなっているそうで、相談者の方はこのまま泣き寝入りするしかないのかと、憔悴しておられました。
制度はあるが認められるハードルは高い
知識なく不動産投資に手を出してしまい、悪徳業者の思うツボ――。こういった例はなかなか後を絶ちませんし、業者相手に集団訴訟に踏み切る方々もいるなど、社会問題化しています。では、騙されてしまった側には救済策はまったくないのでしょうか?
結論から言うと、救済の可能性がある制度はあっても、その申立てが認められることは非常にハードルが高い、というのが現状です。また訴訟を起こしても損害賠償請求が認められない判例もあり、お金と時間をかけても結局、損害を被ることになるというケースもあります。
たとえば、こんな裁判例がありました。
—————-
◆判示事項:
原告が、被告の担当者から住宅ローン(フラット35)の利用が可能であると騙されて同ローンを利用して投資用目的で不動産を購入したところ、ローンの債権者から上記目的で融資を受けたことが契約違反に当たるとして借入金の一括返済を求められたとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案。
裁判所は、原告は上記目的でフラット35を利用することが融資契約の違反となることを契約の締結前に認識していたとし、原告は、自己居住用住宅の購入目的と装って融資契約を締結したものであり、契約違反にならないと誤信して融資契約を締結したとはいえず、被告の勧誘行為と融資契約違反の発覚で原告が被ったとする損害との間に相当因果関係は認められないとして、請求を棄却した事例。
————–
「わかっていながら締結した」とみなされてしまう
原告は20代の女性で、不動産購入は未経験。彼女には当時、クレジットカードリボ払いの負債がありました。そんななか、知人と、知人から紹介された不動産業者に不動産投資を勧められ、フラット35を使って投資物件を購入。しかし途中でそれが金融機関の知るところとなり、契約違反で一括返済に。原告女性は、不動産業者に騙されたと損害賠償請求の裁判を起こしました。
判決の主文を見ると、不動産業者は女性に、「住宅ローンで不動産投資はみんなやっているから気にする必要はない」「金融機関が住宅ローンを不動産投資に使うことは契約違反と説明しても、それは形式的なもの。わかりました、と答えればよい」などと話していたと書かれています。
しかし判決は、原告の請求を棄却。
さらに主文を読んでいくと、女性は不動産業者のこういった説明を信じ込んでいたことや、途中、契約締結を中止するタイミングはあったが実際には自ら動くことはなかった。金融機関の「住宅ローンで不動産投資はNG」の説明も、不安に思いつつも「わかりました」と答えていた――等々の理由から、女性が一方的に「騙されただけ」ということではなく、「被告が原告に対して不法行為責任を負うとは認められない」「これを棄却する」という判決で結ばれていました。
“悪徳”の人たちにとっては丸め込むなど容易い
本当に厳しいなと思います。当NPOへの相談者の方の話を読んでいるようで、私もやるせない気持ちになってきます。ここで個人的な見解を書くことは控えますが、知識や経験の浅い若い世代を丸め込んで誘導し、騙すなど、“悪徳”の人たちにとっては赤子の手をひねるようなものです。
提訴から判決までは約2年。費やされた年月と費用は、取り戻すことはできません。
ただ……、少し矛盾するようではありますが、何もせずにただ泣き寝入りするくらいなら、辛くても行動に移してみるべきだとも思います。何でも、動かないよりは動いてみたほうがいい。トラブルを乗り越えるためには、そのくらいの胆力も必要なことは事実です。
一般消費者を守るための「保証金」
「弁済業務保証金」という言葉を聞かれたことはありますか?
これは、宅建業者が不動産開業時に保証協会(全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)か、不動産保証協会(ウサギマーク))に加入。弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会がその金額を供託所に供託する団体保証の制度のことです。分担金は、開業時に本社で60万円、支社がある場合は各30万円を保証協会に納付します。
もうひとつ「営業保証金」というものもあり、こちらは本社で1000万円、支社で各500万円を法務局へ供託する制度です。
宅建業者は、開業時にいずれかの方法で必ず保証金を供託する必要がありますが、営業保証金は高額のため、だいたいは「ハト」か「ウサギ」の保証協会に加入し、保証金の供託義務を満たすというのが一般的です。
不動産は高額なので、売買の際にもし何かトラブルがあって損害賠償請求になった場合、取引業者が支払えないことがあるかもしれません。そんな時に、供託する保証金から支払って一般消費者を守ることを目的とした制度です(なお宅建業者同士の取引の場合は、この制度は摘要されません)。
何かあった場合の保証金額は、1社につき上限1000万円(支店がある場合はプラス500万円となるため、上限は1500万円)。ですので、なんらかの宅建業法違反で消費者が不動産業者に騙されたという場合は、その業者と連絡が取れなくなろうが逃げられようが、制度上は、業者の弁済業務保証金もしくは営業保証金から1000万円(~1500万円)までなら還付という形で取り戻すことができます。
「騙されて自己破産しました」では認められない厳しさ
ただ、留意点があります。
まず、投資物件トラブルを例に取ると、1社による被害に遭った人は一人とは限りません。保証金は1社につきの金額ですから、人数によっては、取り戻せる金額は目減りします。申立てて、認証されるのは言わば“早い者順”ですので、申立てた人が10人いたとしても、最初の一人が900万円申立ててそれが通ると、残り100万円をあとの9人で按配しないといけない、という状況になります。
一方で、認証審査の厳しさもあります。
保証協会は一般消費者の意見も不動産業者の意見も、あくまでも中立的な立場できちんと聞く役割です。ここではどちらかが一方的に「損害を与えられた」「騙したわけじゃない」と主張してもすんなり認められるわけではなく、「騙されて残債一括請求になって、自己破産しました」と言うだけでは認証されないケースが普通にあります。
ポイントは、「業者が宅建業法に違反した結果、消費者が被害を被ったかどうか」で、シビアな話ではありますが、不動産業者の説明を受けて契約書に押印したという事実が、前述の判例のように「知っていて合意のうえ、納得して押印した」とみなされても仕方がない局面ではあるのです。
避けたい免許取消し。行政の相談窓口に訴えられたくない業者
認証が通りそうな例で言えば、再建築不可物件にも関わらず、宅建業者が故意に「建築できる」と消費者を騙して売りつけたが、結局できなくて損害が発生した――というような話でしょうか。明らかに宅建業法違反で損害を被っている状態であれば、当NPOでは弁護士に相談して損害賠償請求を申立てることの他にも、弁済業務保証金申立てについてのアドバイスをするようにしています。
また、不動産業者は中小規模なところも多く、何かトラブルが発生した時に消費者が自治体などの相談窓口に訴える=行政指導が入る、呼び出しがかかる、といったことを非常に嫌がります。内容によっては免許取消しや営業停止処分になる可能性もあるので、これを避けたいのは業者の本音です。
保証金申立ての検討だけでなく、こういったことで業者の対応が多少変わるかも知れません。地道ではありますが、“できる対策”のひとつとして行ってみていただきたいと思います。
「住宅ローンが払えない」というご相談をはじめ、離婚問題、相続問題、債務問題、不動産トラブル、投資物件トラブル等でもお困りのことがありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。ご相談内容に適したアドバイス、専門家の紹介もすべて無料で行っています。まずは何でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
メール、公式LINEでのご相談は24時間受付可能。関東・銀座相談所は、土・日・祝日の無料相談会を行っておりますので、対面や電話でのご相談予約も可能です。
相談所は、関西、中国・四国にもございます。ご相談の場合は各相談室にお問合せください。
【5月の土日祝日無料相談会】
5月24日(土)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
※面談時のマスク着用は、任意とさせていただきます。
電話、メール、オンライン相談(zoom)もご予約可能です。
【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:
https://www.shiennet.or.jp/database2/contact/