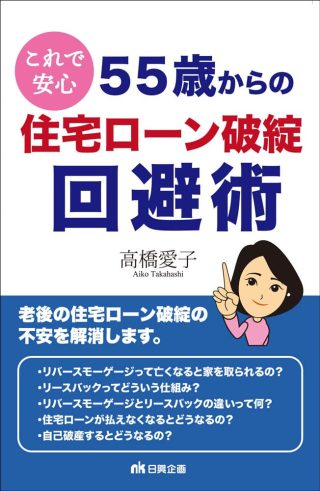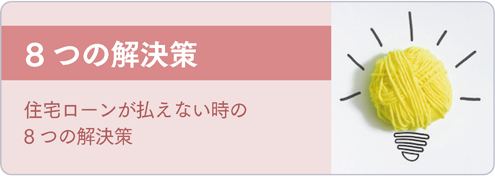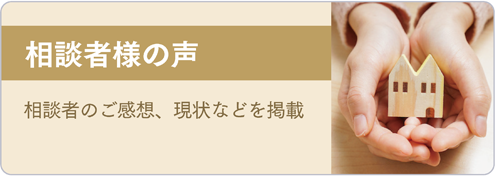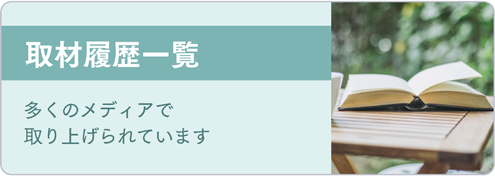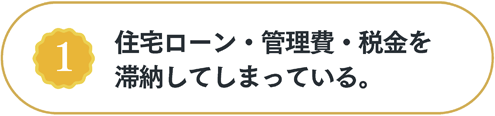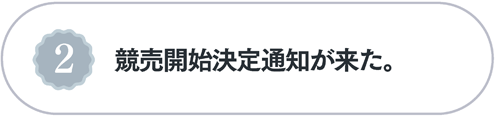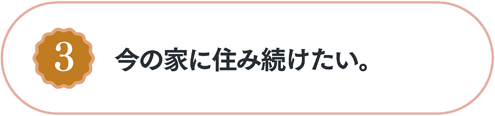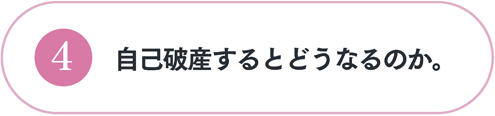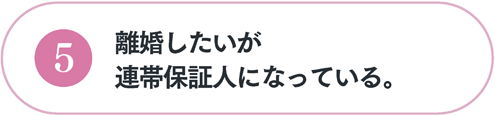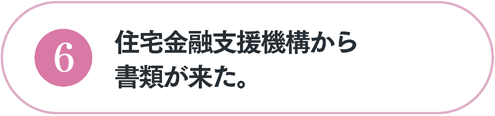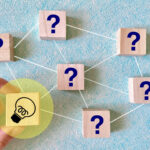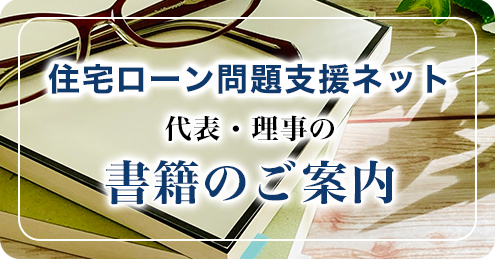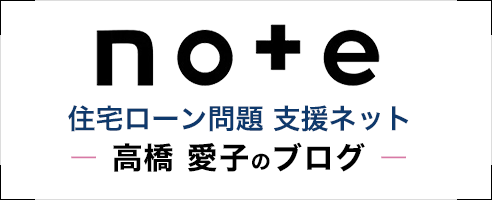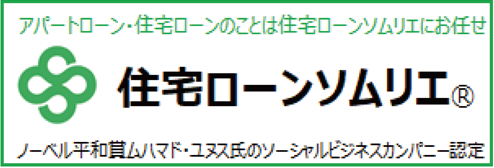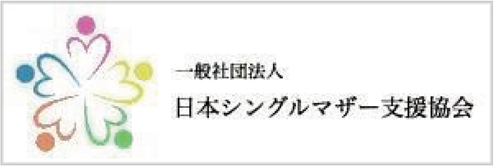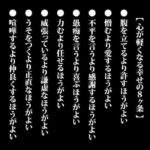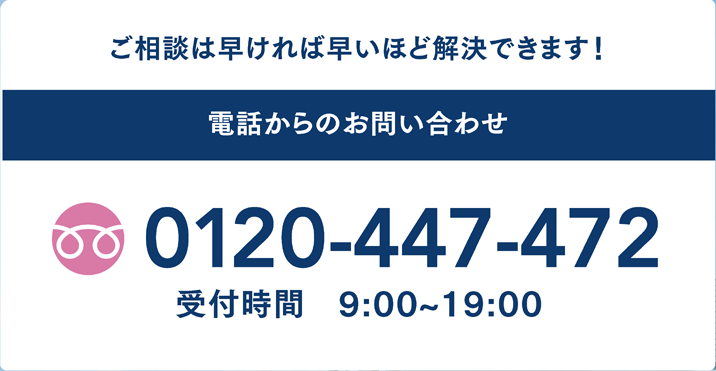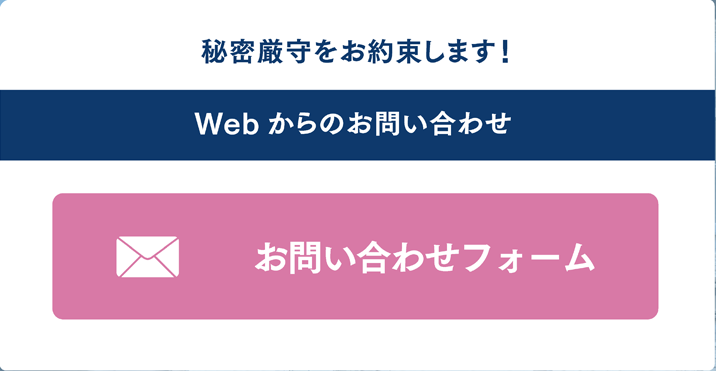住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
不動産にまつわる問題というのは、本当にさまざまなものがあります。高い買い物だけに、基本的には消費者が法律で守られていることは事実なのですが、とはいえ、場合によっては、そうとも言い切れないケースもある。今回は、「不動産のサブリース」について書こうと思います。
以前、ある方から受けた相談がまさにこのサブリース問題でした。結果的に法的整理を選ぶことになり、事態は一応の決着をみましたが、経緯がひどく後味の悪いものでした。
人気のサブリース、最大の注意点は
不動産のサブリースとは、不動産オーナーがサブリース会社にその物件を借り上げてもらい、サブリース会社がさらに同物件を第三者に又貸し(転貸)する仕組みです。この方式では、サブリース会社が物件の入居者募集や管理業務全般を請け負い、不動産オーナーには安定した家賃収入がもたらされます。サブリースは大手のハウスメーカーや賃貸物件建設の会社などでも提供しているサービスですし、CMなどで見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
メリットとして、オーナーは手間のかかる賃貸経営から解放されることが挙げられます。面倒事をいわば〝外注〟できて、入居者募集まで担ってくれる。仮に入居者が埋まらなくても、契約には家賃保証がついているので、オーナーには毎月の家賃収入が支払われます。これは実際、大きなポイントだと思います。
ただ、言うまでもないですが、メリットの裏にはもちろんデメリットも潜んでいる。最も注意しなくてはならない点は、途中、サブリースの会社から突然、家賃収入減額を要求されたり、サブリース契約の解約が難しいことが少なくない、ということです。
オーナーにも業者にも利点がある
たとえば、オーナーをA、サブリース会社をB、Bから借りる第三者をCとしましょう。サブリースの流れはA→B→Cとなります。
Aの持っている不動産の賃料が相場的に10万円だとすると、Bはだいたいその85~80%くらいをAに対する家賃保証として契約します。入居者がいなくても、Aは毎月8万円~8万5,000円の家賃収入が得られるということですね。Aは、BがCに賃貸する内容に関しては関与しないため、BがCに対していくらで貸しているかは把握していません。Bが100%=10万円で貸せばBは15~20%が利益になりますし、110%で貸せばさらに増益です。こんな具合に、一応、不動産のサブリースはオーナーにもサブリース会社にもメリットがある仕組みであり、私も、それ自体に異論があるわけではありません。
あまりに多いグレーゾーン。法整備は2020年6月のこと
しかし、一見メリットばかりありそうな不動産のサブリースは、実はさまざまな問題をはらんでもいるのです。
一番の問題は、サブリース会社が不動産オーナーに契約の詳細をあまり説明していないという点。ここから深刻なトラブルに発展することが実に多い。なかでも、AB間のサブリース契約の解除の難しさ――というか、基本的に解除できないことが大半である、という事実は重くのしかかります。
本来、サブリース契約を締結する時にはBがAに対して重要事項や確認事項を説明する必要がありますが、意外に思われるかも知れませんが、少し前まで、これは法律で義務づけられているものではありませんでした。かなり曖昧なグレーゾーンで、ほかにも、AがBからきちんと説明を受けていなかったことで、たとえば「〇年間の家賃保証があります」と謳っていたサブリースではあっても、5年目に賃料改定があることは知らなかったとか(そしてだいたい、そこで賃料減額を要求されるとか)、それによってAの収支が回らなくなり「騙されたかも」、サブリース契約はいつでも解除できると聞いていたのにできない、というような、かなり深刻なトラブルが消費者センターに殺到した経緯があったのですね。
そこでやっとルールができたのが2020年6月のこと。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:サブリース新法)という法律が公布され、同年12月に施行。この法律により、重要事項説明の義務化や、誇大広告、不当勧誘の禁止が定められました。
オーナーだけが契約違反と言われる?
サブリース契約はれっきとした賃貸借契約であり、借地借家法に基づく以上、借主は保護されるのは当然です。ゆえに、オーナーが「物件を高く売りたいから解除してほしい」と訴えても、それだけでは解除は認められません。
問題なのは、そもそも本来使ってはいけない「住宅ローンで投資物件を買わせる」といった違法行為が前提にあるケースです。そのような経緯をつくった業者がサブリース契約の借主(B)であったり、その業者からサブリース会社を紹介されたケースです。
売買とサブリース契約がセットでAには選択の余地も与えられず、契約書すら交付されていないというケースもありました。このような場合、オーナーであるAだけが違法だ、契約違反だとされ、自己破産に追い込まれる現状には大きな疑問を感じます。
「正当事由」の難しさ
借地借家法では、貸主側(A)から賃貸借契約を解約・解除するには、一定の解約予告に加えて「正当事由」が必要とされています。
一方で、サブリース契約などの内容によっては「解除する場合は半年ほど前に申し出、家賃1年分を違約金として支払う」といった条項が盛り込まれているケースもあります。しかし実際には、こうした条項に従って1年分を支払えば解除できるわけではありません。借主側(サブリース会社など)は「借地借家法で保護されているため、解除には応じられません」と主張してくることもあるからです。
この「正当事由」という要件は非常に厄介で、法的に認められるには相応の理由が必要です。裁判例でもさまざまな議論が重ねられてきましたが、たとえ正当事由が認められたとしても、そのまま契約が解除されるわけではなく、実務上は立退料など相当額の金銭的保証を行わなければならないのがほとんどです。
つまり、「正当事由」は単なる形式的な要件ではなく、実際に大きなハードルであり、貸主にとっても慎重な対応が求められるのです。
「借地借家法に守られている」ので
Bの悪質な行為によって窮地に追い込まれているA。しかし、サブリース会社(B)は借地借家法を盾に「解除できない」と突っぱねる。こんなことがまかり通ってよいのでしょうか。
Aは、不正ともいえる融資を組まされ、賃料も不透明、賃借人の属性すら明らかでない「ブラックボックス化したサブリース契約」の渦中に置かれていました。こうした契約が付いている物件は売却がしづらく、売れたとしても安価になってしまうのが現実です。
もちろん、Aがここまで追い込まれたのは自己責任の部分もあるでしょう。しかし、最後の望みとして「せめて高く売却し、自己破産を避けたい。違約金も払うので解除してほしい」と訴えるAに対し、サブリース会社は「借地借家法があるので応じない(=自分たちは借地借家法に守られているので応じる必要はない)」と頑なに拒む――。こうした事例は決して少なくありません。
これが「法の建前」と「人の暮らし」との間に横たわる深い溝です。そこに立ち会うとき、強い義憤を感じざるを得ません。
「サブサブ」というカオスからの法的整理
冒頭の相談者の方に話を戻します。この方も同様のケースでサブリース会社に折衝し、家賃1年分の違約
金を払うとで解約合意。ようやくサブリース契約を解除してもらいました。ところが、その先にさらなる落とし穴が待っていました。なんと、BがAから借り上げた物件について、Bは第三者Cと別のサブリース契約を結び、さらにそのCがエンドユーザーDに転貸していたのです。
つまり、
A → B:最初のサブリース契約
B → C:Aの知らないところで結ばれた契約
C → D:実際に入居しているのは賃借人D
という「多重構造」が存在していたのです。業界ではこれを「サブサブ」と呼びます。
この構造では、Aから借り上げた物件がDに貸し出されるまでの間に、BとCがどれだけ利ざやを抜いているのかはブラックボックスです。そして、違約金を払いながらも救済されないAだけが窮地に追い込まれてしまいます。
「売らざるを得ないからサブリースを外したい」というAと、「違約金を払えば解除する」というBの合意までは成立していました。にもかかわらず、BはCとの契約の存在を伏せていた。これは極めて悪質であると言わざるを得ません。
結局、この「サブサブ」というトラップに囚われてしまった相談者の方は、サブリース契約がついたままでは希望金額で売却できず、オーバーローンを解消できないことが早い段階で確定しました。少しでも高く売却して自己破産を避けようと懸命に努力しましたが、複雑なサブサブ契約のブラックボックスに阻まれ、法的整理の道を選択。破産管財人に物件売却をゆだねることになりました。
数万円の利ざやのために一人の人生が変わる
自己破産に追い込まれる前に、できる限りの対応をして頑張ってこられた方の事例でした。それだけに、後味のよくない結果となりました。
もちろん、AB間の契約を無条件に外してほしいと主張するつもりはありません。ただ、宅建業者という専門家でありながら、契約違反となる融資を組ませ、投資物件購入を指南した業者が、その後は借地借家法という強力な盾を使って一切サブリース解除に応じないという姿勢には、大きな疑問を抱きます。
その結果、経済的に追い込まれ、人生が大きく変わってしまう人がいる。にもかかわらず、「法律的には経済的破綻は正当事由にはならない」という一点で押し切るのは、本当に正しいことなのでしょうか。
結局、その物件は競売にかかり、サブリース契約も競落人には原則対抗できません。転借人も一定の猶予期間を経て退去せざるを得なくなるのです。つまり、毎月数万円の差額を得るために、一人の人生を追い詰めてしまう構造がそこにあります。
法律上の判断と人道的な判断は、いつまでも平行線のままなのでしょうか。借地借家法の「正当事由」が持つ重みと限界、そして不動産実務の現場で起きている矛盾を、改めて考えさせられる事例でした。
いまはサブリース新法ができましたから、事前に説明を必ず受けられますが、とはいえ、契約に挑む個人個人が、やはり最低限の知識は身につけておいてほしいと、心から思います。家賃保証は魅力的に聞こえるかもしれませんが、まずは、そのサブリース業者は大丈夫なのか、信頼できる会社なのか、調べたり専門家に相談してください。当NPOも、セカンドオピニオンでも構いませんから、少しでも疑問や不安に感じることがある場合は、遠慮なく相談にいらしてください。
「住宅ローンが払えない」というご相談をはじめ、離婚問題、相続問題、債務問題、不動産トラブル、投資物件トラブル等でもお困りのことがありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。ご相談内容に適したアドバイス、専門家の紹介も行っています。まずは何でも、ご遠慮なくお問い合わせください。
メール、公式LINEでのご相談は24時間受付可能。関東・銀座相談所は、土・日・祝日の無料相談会を行っておりますので、対面や電話でのご相談予約も可能です。
相談所は、関西、中国・四国にもございます。ご相談の場合は各相談室にお問合せください。
【9月の土日祝日無料相談会】
9月20日(土)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
9月21日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
9月27日(土)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
9月28日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~
※面談時のマスク着用は、任意とさせていただきます。
電話、メール、オンライン相談(zoom)もご予約可能です。
【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:
https://www.shiennet.or.jp/database2/contact/